
パラパラ塩ふるい
- HEALTH
- 2025.07.27
【医師監修】長寿医学の専門家・白澤卓二医師が語る「塩と健康」の新常識|適塩生活と"ふりすぎ"を防ぐ習慣術
食材の味を引き立てるために、欠かせない塩。しかし、「塩=体に悪い」というイメージから、減塩を心がけている人も多いのではないでしょうか。
今回は、塩に含まれる栄養素とその役割、体に良い塩の選び方、摂りすぎを防ぐ生活習慣などについて、長寿医学の専門家である白澤卓二医師に伺いました。
高血圧や腎臓病のリスクを軽減したい方、正しい適塩生活に興味をお持ちの方は、ぜひご一読ください。
塩は健康に悪い?正しい塩との付き合い方とは
厚生労働省が発表した「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、日本人の1日あたりの塩分摂取量(食塩相当量)の目標値は、男性7.5g未満、女性6.5g未満に設定されています。さらに、WHO(世界保健機関)が推奨する1日あたりの塩分摂取量は5g未満。このことから、「塩分摂取量が少ないほど健康に良い」というイメージが根づいているのです。
その一方で近年、世界各国の研究機関では、それに反するエビデンスが次々と示されています。それでは、どのようなポイントに注意して塩を摂取すれば良いのでしょうか。

塩は私たちの体に欠かせない栄養素
人間の体液中には、常に0.9%の濃度で塩分が含まれています。体内に入った塩は、水に溶けると「ナトリウムイオン」と「塩化物イオン」に電離し、体中に電気を通す働きをします。それによって、
- 細胞内外の圧力(浸透圧)を調整する
- 食べ物の消化・吸収を助ける
- 汗を出して体温を調整する
- 神経や筋肉の働きを調整する
- 食欲や味覚を正常に保つ
などの生理的機能をサポートしてくれるのです。
なぜ「塩=悪い」のイメージが広まったのか
ひと昔前まで塩は入手しづらく、貴重な資源でした。日本で塩が入手しやすくなったのは、1971年以降のこと。「食卓塩」と呼ばれる精製塩の製造が本格化し、大量生産が可能になったことで、一般の人々も安価で買えるようになりました。
一方、精製塩の消費が増えるにつれ、別の問題も浮上します。「塩分の過剰摂取が高血圧の原因になる」という医学的研究が注目されるようになったのです。
「塩=体に悪い」というイメージが広まったのは、一般家庭に精製塩が広く普及したことが、深く関係していると言えるでしょう。

自然塩と精製塩の違い|選ぶべき塩は?
自然塩と精製塩は、似ているようで全く異なります。自然塩には塩化ナトリウムが約8割、ミネラル分が約2割含まれていますが、精製塩は、約99%が塩化ナトリウムでできているのです。
精製塩は、ほぼ単一成分で構成されているため、過剰に摂取すると体内成分のバランスを崩し、高血圧につながる可能性があります。
その一方で自然塩に含まれるカリウムはナトリウムの過剰摂取にブレーキをかけ、塩化ナトリウムの副作用の緩和が期待できます。さらに、自然塩なら現代人に不足しがちといわれるマグネシウムも補えます。
つまり、大切なのは、「体にいい自然塩を選ぶこと」なのです。
「塩」と健康の深い関係|最新研究が示す「適塩生活」のすすめ
塩分が不足すると体にどんな影響がある?
塩に含まれるナトリウムは、健康維持に欠かせない必須ミネラルの一つです。ナトリウムが不足すると、食欲や集中力、筋力の低下といった症状が現れ、ひどくなると痙攣を引き起こしたり、昏睡状態に陥ったりすることもあるといわれています。

暑い時期に注意が必要な「熱中症」も、塩分不足による代表的な症状として知られています。減塩しすぎることで、思わぬ体調不良を招くおそれもあるのです。
塩分の摂りすぎによる健康リスクとは
塩化ナトリウムを一挙に大量摂取すると血液中の塩分濃度が上がり、喉の渇き、むくみ、血圧の上昇などの症状が現れます。
さらに、塩分の摂取過多が続くと、高血圧、腎臓病、心臓病などのリスクが高まる恐れがあります。
日本人が塩分を多く摂るのは理に適っている
日本の夏は高温多湿で、たくさんの汗をかきやすいため、水分や塩分を適切に補給しなければなりません。そのため、日本人が漬物や佃煮などの塩分が多い食べ物を好むのは、理に適っているとも考えられます。
自然塩が健康に良い理由|ミネラルの役割と効果

自然塩のミネラルがもたらす5つのメリット
自然塩の大きな特徴は、多種多様なミネラルが含まれていることです。五大栄養素の一つであるミネラルは、臓器や細胞の活動をサポートしたり、歯や骨のもとになったりと重要な役割を果たしています。下記で具体的なメリットを紹介します。
①美肌・アンチエイジング効果
自然塩のなかでも特に海塩は、美肌やアンチエイジング効果が期待できます。肌のターンオーバーを促進するカルシウム、バリア機能を高めるマグネシウム、保湿効果があるカリウムなどのミネラルは、肌の代謝や保湿、修復をサポートしてくれます。
②高血圧・生活習慣病予防
海塩には、心筋の収縮をコントロールするカリウムや、血圧や血糖値の調節機能を果たすマグネシウムが含まれています。適切に摂取することで、高血圧や生活習慣予防にも役立つ可能性があります。
③デトックス効果
マグネシウムや亜鉛は、体に蓄積した有害重金属の排出を促進します。肝臓や腎臓の働きを助け、デトックス効果が期待できるのです。
④イライラしにくくなる
海塩に含まれる必須ミネラルは、神経機能の調整にも寄与しています。不足するとイライラしたり、疲労感の原因となります。
⑤味覚改善で減塩につながる
精製塩の「強いナトリウム刺激」は、舌の味覚細胞に負担をかけ、味覚が鈍化・麻痺しやすくなります。すると、さらに濃い味を求め、塩分を摂りすぎる傾向になりがちなのです。
一方、自然塩に含まれるミネラルは塩味を和らげ、うま味やコクを加える働きをします。ミネラルによって刺激が緩和されるため、繊細な味覚を取り戻しやすくなります。少ない量でも食材の味を引き立てるため、結果的に減塩や味覚改善が期待できるのです。

医師が教える、今日からできる「塩との賢い付き合い方」5選
健康的に塩を摂取するための、具体的な実践法を紹介します。
ポイント①精製塩から自然塩に変える
自然塩はミネラルバランスが良く、味もまろやかです。少量で舌も満足しやすいため、自然塩に置き換えるだけで、減塩につながります。
ポイント②素材本来のうま味を引き出す調理を
蒸す、焼く、ローストなど、素材の甘さやうま味を引き出す調理方法を使うと、塩分が控えめでもおいしく味わえます。
また、素材に水分が残っていると薄味に感じるため、調理前に食材の水気を取るようにすることをおすすめします。
さらに、食材を薄切りにしたり、細長い形に切ると表面積が増えて調味料がよく絡みます。
それにより、薄味でも最初の一口で満足を得られやすくなります。
ポイント③加工食品や外食の塩分を見直す

ハムやソーセージなどの加工肉、インスタント食品には、意外と多くの塩分が含まれています。選ぶときはパッケージに記載された「食塩相当量」をチェックし、「1g未満/100g」と書かれたものや、「減塩」「無塩」タイプのものを選ぶようにしましょう。
また、ソースや醤油、ドレッシングには、意外と塩分が含まれています。忙しくてスーパーやコンビニの弁当、外食を利用するときは、
- 弁当に添えられた醤油やソースの使用を控える
- 外食時は「ソースやタレは別添えにしてください」と注文時に一言添える
- ラーメンのスープを飲み干さない
などの点に注意して、減塩の積み重ねを心がけましょう。
ポイント④塩を使うのは最後のひと振り
ダシのうま味や香味野菜の香り、柑橘類の酸味を活用して、素材本来の味を引き立てると、塩が少なめでも満足感が得られやすいでしょう。
また、調理時に塩を使うのは、仕上げのひとふりに。パラパラとふりかけるだけで、味がひきしまります。
ポイント⑤道具を工夫して"ふりすぎ"を防ぐ
塩のふりすぎを防ぐには、スプーンなどの小さな計量器具を使うと、正確に測ることができます。指でひとつまみするときは、事前に手をよく拭いておくと必要以上に塩が手に残らず、無駄なく使えます。
また、湿気によって塩が固まると、ふりかけるときにドバッと出てしまうことも。密閉容器で保存したり、乾燥剤や珪藻土スティックを容器に入れるなどの対策で、塩が固まるのを防ぎましょう。

"ふりすぎ"を防ぐ!「パラパラ塩ふるい」で適塩習慣
塩をスプーンや指先で均一に塩をふりかけるのは案外難しく、困ったことはありませんか。
そんな悩みから生まれた便利グッズが「パラパラ塩ふるい」です。
パラパラ塩ふるいのスプーンは、片手でスライド操作ができるので、さっとすくって、すりきるだけで、約小さじ1杯(6g)の塩が計量できます。
調味料入れに入るコンパクトサイズなので、余った塩はそのまま戻せます。
また、スプーンの穴あきカバーは、粗塩と粒の細かい塩のどちらにも対応可能です。粒の大きな塩の場合は穴の向きを下向きに、サラサラの塩をふるときは穴を上向きにして左右にふれば、かけすぎを防げます。
さらに、分解して洗えるので、お手入れも簡単。便利グッズを上手に利用して、気軽に適塩生活を始めませんか。
まとめ|正しい知識で「塩と健康」を見直そう
「減塩=健康に良い」というイメージがありますが、極端な減塩はミネラル不足を招き、倦怠感や食欲不振、低血圧などのリスクを高める可能性もあるのです。
大切なのは、良質な塩を適量に摂取すること。減塩しすぎず、過剰摂取もしない「適塩生活」で、塩と健康的に付き合いましょう。
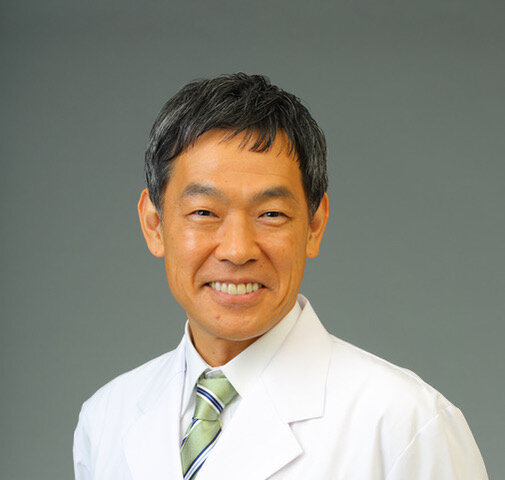
執筆者プロフィール
白澤卓二/医学博士
順天堂大学大学院教授などを経て白澤抗加齢医学研究所所長、お茶の水健康長寿クリニック院長に就任。専門は寿命制御遺伝子の分子遺伝学、アルツハイマー病の分子生物学、アスリートの遺伝子研究。多数のメディア出演をはじめ、『すごい塩』『免疫力を高める塩レシピ』など、著書は300冊を超える。
関連サイト/https://ohlclinic.jp/
関連商品はこちら

RECOMMEND

鉄のことり
【医師監修】鉄分不足が招く肌荒れ・抜け毛の原因|血液専門医・濱木珠恵医師が解説する美容と鉄分補給のコツ
体の不調、原因は「鉄分不足」かも?日本血液学会認定血液専門医の濱木珠恵先生に、鉄分の役割や不足で起こるトラブル、無理なく補うコツについて伺いました。
- HEALTH
- 2026.01.21

ぬかどこボックス
ぬか漬けはなぜ美容・ダイエットにいいのか?腸活で美肌&痩せ体質をつくる方法【腸活アドバイザーyukariさん監修】
腸活フードとして注目されるぬか漬け。腸活アドバイザーのyukariさんにぬか漬けが美肌やダイエットに効果的な理由、手軽に続けられるコツについて伺いました。
- HEALTH
- 2025.12.16

ロカポット
油は健康の味方!専門家が語る、健康に良い油の選び方と正しい摂り方
「油」は私たちの健康を支える大切な栄養素。今回は油の健康効果について慶應義塾大学医学部化学教室・教授・井上浩義先生に詳しくお話を伺いました。
- HEALTH
- 2025.11.19

炭グリル
【医師監修】魚が生活習慣病・糖尿病予防に役立つ理由とは?専門医が語る魚の健康効果と食べ方
「魚は体に良い」という話はよく耳にしますが、具体的にどのような健康効果があるのでしょうか。糖尿病専門医の恩田美湖先生に詳しくお話を伺いました。
- FOOD
- 2025.10.22




