
炭グリル
- FOOD
- 2025.10.22
【医師監修】魚が生活習慣病・糖尿病予防に役立つ理由とは?専門医が語る魚の健康効果と食べ方
「魚は体に良い」という話はよく耳にしますよね。しかし、具体的にどのような健康効果があるのか、また、なぜそれが生活習慣病や糖尿病の予防に繋がるのか、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、魚がもたらす健康効果と栄養的な役割、食べる頻度や量の目安、手軽に魚料理を取り入れるための工夫について、糖尿病専門医・恩田美湖先生に話を伺いました。生活習慣病や糖尿病のリスクを低減したい方、健康的な食生活を目指したい方は、ぜひご一読ください。
予防医療の専門家が語る、魚の健康効果とは
高血糖や中性脂肪の上昇は、血管内皮にダメージを与え、血管の機能が低下します。血管機能の低下は、高血圧や脂質異常症、動脈硬化性疾患のリスクを高め、糖尿病の合併症進行にも深く関与します。食生活の改善や運動などによってこうしたリスクを軽減し、「病気にならないこと」を目指すのが予防医療の役割です。

予防医療において、食生活の改善は重要な柱の一つです。その中でも魚は、その豊富な栄養素が、健康寿命の延伸に大きな効果を発揮すると考えられています。
ここでは、糖尿病専門医として、魚の健康効果について解説します。
魚の健康効果①:糖尿病や生活習慣病予防に役立つ
魚には、良質なたんぱく質やオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)が豊富に含まれており、血糖値の安定化、中性脂肪の低下、動脈硬化の予防など、さまざまな生活習慣病のリスク低減に貢献するとされています。

特に青魚(サバ、イワシ、サンマ、アジ、ブリなど)は、DHA・EPAを多く含んでおり、慢性的な炎症の抑制や血流改善に役立つと報告されています。
魚の健康効果②:脂肪肝の進行を防ぐ可能性がある

青魚に含まれるDHAやEPAは、肝臓に脂肪が蓄積するのを防ぐ働きがあるとされ、脂肪肝の進行予防に役立つ可能性があります。
脂肪肝(特に非アルコール性脂肪性肝疾患=NAFLD)は、2型糖尿病やメタボリックシンドロームと深く関連しており、進行すると生活習慣病のリスクを高めることが知られています。
魚を定期的に食事に取り入れることは、肝機能の維持や生活習慣病予防に貢献する可能性があります。
魚の健康効果③:筋力維持・抗酸化作用で全身の健康を支える
魚には、筋肉の維持に必要なたんぱく質や、その代謝を助けるビタミンB群が含まれています。これらの栄養素は、筋力の低下予防や疲労回復のサポートに役立つとされており、健康的な身体づくりを支えます。
さらに、魚にはオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)のほかにも、抗酸化作用が期待されるミネラル(セレン)やビタミンEなども含まれています。これらの栄養素は、酸化ストレスから体を守り、加齢に伴う体調変化の予防にも役立つ可能性があることから、魚は全身の健康を支える機能性食品として注目されています。
魚を健康的に取り入れるためのポイント
魚の摂取量の目安と日常での取り入れ方
厚生労働省が推奨する量の目安としては、大人であれば1回の食事で80gから100gほど。
イワシやアジ、サバなどの青魚を一尾、あるいは切り身一切れ程度食べれば、十分に目安量を満たすことができます。

また、鯛やヒラメ、カレイなどの白身魚は脂肪分が少なく、消化にもやさしいため、低カロリーなタンパク源として活用できます。こうした魚をメニューに加えることで、カロリー調整もしやすくなり、糖尿病や生活習慣病の食事管理にも役立ちます。
魚を選ぶ際の注意点
ただし、マグロやカジキなどの大型魚は、水銀を比較的多く含む可能性があるため、妊娠中の方や乳幼児は摂取量に注意が必要です。厚生労働省の指針なども参考に、バランスの取れた魚の摂取を心がけましょう。
魚の健康効果を高める食べ方・調理の工夫
栄養を守るための魚の調理法とは?
魚に多く含まれるDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸は、高温や酸素に弱く、酸化しやすい性質があります。そのため、これらの成分を効率よく摂取するには、酸化を防ぐ調理方法を選ぶことが重要です。
刺身などの生食が最も栄養を保ちやすい方法ですが、加熱する場合は、なるべく短時間で調理し、できるだけ早く出来立てを食べることが望ましいとされています。また、調理後すぐに食べられない場合は、空気に触れないよう密閉し、冷蔵または冷凍保存することで、栄養の劣化を抑えられます。
抗酸化食材と組み合わせる
魚の栄養価を保つには、レモンやビタミンEを含む香草類、オリーブオイルなどの抗酸化食材をあわせて使うのも効果的です。酸化を防ぐだけでなく、風味も引き立ちます。

また、柑橘類の酸味や、香草、ショウガやニンニク等の薬味、昆布や鰹節などのダシを活用することで、塩分を控えつつ満足感の高い味付けが可能になります。糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を意識した食事管理にも有効です。
血糖値の急上昇を防ぐ食べ方のポイント
血糖値が急激に上がると、体に負担がかかります。特に糖尿病の方は、「ゆっくり食べる」「よく噛む」ことで、糖質の吸収スピードをゆるやかにし、血糖値の急上昇を防ぐことができます。
糖質の吸収を抑える食べる順番
食べる順番にも工夫が必要です。まずは野菜や海藻などの食物繊維を含む食材から食べることで、糖や脂肪の吸収をゆるやかにする効果が期待されます。
次に魚や肉などのタンパク質を摂り、最後にご飯やパンなどの炭水化物を食べることで、血糖値のコントロールや食べすぎ防止にもつながります。
食習慣の見直しが生活習慣病予防の第一歩
調理法や食べ方、食べる順番を少し意識するだけでも、魚に含まれる栄養素を効率よく取り入れることができます。毎日の食事を楽しみながら、腹八分目を意識した食習慣を続けることが、糖尿病や生活習慣病の予防につながります。
魚を無理なく食生活に取り入れる方法
手軽な魚料理から始めよう
魚を食べる機会が少ない方や、料理が苦手な方は、魚料理を食べることはハードルが高いと感じてしまうかもしれません。しかし、無理なく続けるためには、手軽な方法から始めることがポイントです。

たとえば
- 青魚や白身魚のお刺身
- 魚肉ソーセージ
- 魚の缶詰
などは、加熱や下ごしらえの手間がなく、すぐに取り入れやすい食材です。
継続できる"自分に合った魚の食べ方"を見つける
大切なのは、無理なく続けられるスタイルを見つけることです。ご自身の生活リズムや味の好みに合った形で、魚を日常の中に取り入れていくことで、自然と健康意識が高まり、糖尿病や生活習慣病の予防・管理にもつながります。
「炭グリル」で極上の焼き魚を手軽に楽しもう
健康のために魚料理を取り入れたいけど「調理するのが面倒」「火加減が難しそう」と、思う人もいるのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのが、家庭のコンロで使える本格魚焼き器「大人の焼魚・炭グリル」です。
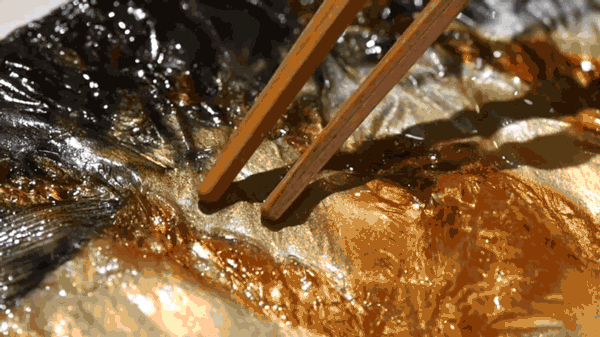
独自開発した「炭プレート」による遠赤外線効果と、熱循環を考慮した蓋の形状により、中はふっくら、外はパリッとした理想的な焼き魚に仕上がるのが特長です。まるで七輪で焼いたかのような風味を、自宅でも気軽に楽しめます。

さらに、プレートとフレームは焦げ付きにくいフッ素コーティング仕上げで、お手入れも簡単。丸洗い可能なので、忙しい方でも継続して使いやすい構造です。健康のために、そして毎日の食事をもっと楽しむために。焼き魚のある暮らしを、「炭グリル」で始めてみませんか。
関連商品はこちら

RECOMMEND

ぬかどこボックス
ぬか漬けはなぜ美容・ダイエットにいいのか?腸活で美肌&痩せ体質をつくる方法【腸活アドバイザーyukariさん監修】
腸活フードとして注目されるぬか漬け。腸活アドバイザーのyukariさんにぬか漬けが美肌やダイエットに効果的な理由、手軽に続けられるコツについて伺いました。
- HEALTH
- 2025.12.16

ロカポット
油は健康の味方!専門家が語る、健康に良い油の選び方と正しい摂り方
「油」は私たちの健康を支える大切な栄養素。今回は油の健康効果について慶應義塾大学医学部化学教室・教授・井上浩義先生に詳しくお話を伺いました。
- HEALTH
- 2025.11.19

ぬかどこボックス
糠漬けアーティスト・市川菜緒子さんが教える、ぬか床の育て方と続け方の秘訣
腸内環境の改善など健康効果も期待できる日本の伝統食・ぬか漬け。今回お話をお聞きした のは、糠漬けアーティストの市川菜緒子さんです。
- FOOD
- 2025.09.17

スチームクッカー
魚は美容と健康の味方!DHA・EPAの効果とおいしく食べるコツ【管理栄養士/美容アドバイザー豊田愛魅さん監修】
美容と健康を同時に叶える食材「魚」。魚の美容効果や簡単でおいしい食べ方などを管理栄養士であり美容アドバイザーの豊田愛魅さんに教えていただきました。
- FOOD
- 2025.08.27




